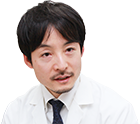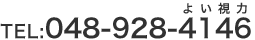『子供の目薬、どうやってやればいいですか?』
というご質問をよくいただきます。
まず、一番わかりやすいやり方をご紹介します。
①目薬をする人は正座して、両足をひろげます。
②子供は顔を上に向けて横になります。
③ひろげた両足で頭を軽く挟み、固定します。
④下まぶたを軽く下に下げます。(あっかんべーの要領で)
⑤下まぶたに目薬をするイメージで点眼します(目の正面だと、目薬の先端が見えるので、子供はいやがります)
ただし、子供がいやがって大暴れした状態ですと、目薬はとても難しいです。また、無理やり目薬しても、その後泣いてしまうと、目薬が涙と一緒に流れてしまい、意味がありません。
そのため、無理やり目薬するのは、あまりおススメしません。
もし、子供がいやがって、目薬をするのが難しい場合、子供が寝ているときはわりとやりやすいため、オススメです。
『黒いものが飛んで見える』
『髪の毛のようなものが動いて見える』
『アメーバみたいなのが見える』
などの症状を『飛蚊症』と言います。
多くの場合、自然に出てくるもので悪いものではありません。
ただし、治療法はないので、そのまま様子を見ることになります。
一方、まれに『網膜剥離』や『硝子体出血』などの病気の症状として出てくることがあります。
特に『墨汁を流したような黒い(赤い)ものが見える』などの飛蚊症の量が多い場合、これらの病気が原因となっている可能性があります。
病気が原因の場合、病気に応じた治療を要します。
特に、網膜剥離では、緊急でレーザーや手術が必要となります。
飛蚊症が自然に出たものか、病気が原因か、自覚症状で判別するのは困難です。そのため、眼科で検査をすることをお勧めします。網膜剥離の場合、緊急での対応が必要となるため、飛蚊症が出た際には、なるべく早めに受診したほうがよいです。
飛蚊症に対する検査として、目薬で瞳を開く『散瞳検査』を行います。この目薬をさすと、5時間程度見えにくくなり、車の運転や細かい字を見る作業などができなくなります。
そのため、眼科受診の際は、車やバイクではなく、徒歩や公共交通機関を利用してください。
また、目薬の効果が出るまでに時間がかかるため、当院では診療終了時刻の1時間前までの受診が必要となります。
時間には余裕をもって、お越しください。
健康診断などで、眼圧が高い(高眼圧)と指摘されることがあります。
眼圧が高いと、視神経が障害される『緑内障』になっている、もしくは、今後なりやすい恐れがあります。
眼圧はよっぽど高くない限り、自覚症状が出ません。そのため、自覚症状がなくても、眼科で精査することが望ましいです。
眼科に受診した場合、眼圧と視野検査を中心に検査を進めていきます。
眼圧は、日や時間により変動します。また、目に力が入ると、実際より高い数値がでることがあるので、注意が必要です
視野検査に異常がある場合、緑内障と診断して、緑内障治療を開始します。
視野検査に異常がない場合、眼圧が25mmHg以下であれば、経過観察となります。眼圧が25mmHg以上の数値が続くようですと、今後緑内障になる可能性が高いため、緑内障治療を開始します。
緑内障は、自覚症状が出たときには、すでにかなり進行しており、手遅れになっていることが多いため、早めに眼科へ受診することをオススメします。

今月もスタッフが置き看板を書いてくれました。
ありがとうございます。
うなぎのうな次郎、だそうです。
(最初、ウナ太郎と記載しておりましたが、正確にはうな次郎でした。お詫びして訂正致します)
Q 処方箋の有効期限はなぜあるのですか?
A 診察を受けてから時間が経過するほど必要な治療が変わってくる可能性が高くなるためです。
Q 処方箋の有効期限はどれくらいですか?
A 発行日を含めて4日間です。これは『保険医療機関及び保険医療療養担当規則』により定められています。この4日間の中には、土日祝日も含まれます。
4日あれば、土日をはさんでも、薬を受け取れる可能性が高いことと、病状は刻々と変わるものであり、診療を受けてから時間が経過すればするほど必要な治療が変わる可能性が高くなるからです。
診察を受けて処方箋を受け取ったら、その足で薬局に寄って薬をもらうことを推奨します。
緑内障の治療について、今わかっていることは
『眼圧を下げると、進行が遅くなる』
この1点のみです。
これは、緑内障には、眼圧の高いタイプだけでなく、眼圧が正常である正常眼圧緑内障にも当てはまります。
同じ眼圧でも緑内障になる人、ならない人がいるように、眼圧以外の様々な要素が関与していることが予測されますが、現時点で確定的に証明されているものはありません。
そのため、『治療は眼圧を下げる』ことのみとなります。
しかし、治療をしても、進行を遅くするのみで、改善や進行を完全に止めることは、今の医学ではできません。そのため、早期発見・早期治療が重要となります。
眼圧を下げる方法は、目薬か手術となります。
目薬はいくつか種類があるため、目の状況などから、使用する目薬を決めていきます。効果が不十分の場合は、目薬の変更や追加を検討していきます。
『緑内障は手術できますか?』
という質問をよくいただきます。
手術も、目薬同様に眼圧を下げるだけで、視力や視野が改善することはありません。しかも、手術は合併症が生じる可能性があるため、目薬でどうしてもコントロールできない場合にしかたなく行う、という位置づけです。
『生活に注意点はありますか?緑内障や眼圧にいいこと、悪いことはありますか?』
これもよくいただく質問ですが、答えは、『現時点では一切わかっていない』となります。
そのため、目薬をしっかり継続することが重要です。
緑内障では、視野が障害されます。しかし、視野の中心部は比較的末期まで温存されるため、視力は変わらないことが多いです。そのため、緑内障は、自覚症状が出にくいです。
視野障害は、信号や看板を見落とす、人や壁などにぶつかりやすい、本の行を読み飛ばす、など『気が付かずに見落とす』という症状が出ることが多いです。
自覚症状が出にくいことのデメリットは、発見が遅れることです。そのため、健診が重要となります。
一方、緑内障があっても、初期の段階ではあまり生活に支障が出ません。そのため、早期発見・早期治療を行い、初期段階にとどめることで、緑内障があっても、ほとんど困ることなく生活を送ることが可能となります。
健診で
・視神経乳頭陥凹拡大
・視神経線維層欠損
と指摘されることがあります。
これらは、『緑内障疑い』を意味します。
緑内障は視神経が障害され、視野が狭くなる病気です。しかし、緑内障は自覚症状が出にくく、自覚症状が出たときには、すでにかなり進行していることが多いです。
そして、緑内障の治療は、今の医学では
『進行を遅くする』
ことしかできません。
そのため、早期発見・早期治療が重要となります。
診断は、眼科で眼圧測定や視野検査などの検査が必要となります。
健診で視神経乳頭陥凹拡大などの指摘を受けたら、放置せずに一度眼科を受診することをオススメします。
『物がゆがんで見える』という症状は、主に網膜の中心である『黄斑』の障害で起こります。
黄斑の病気は、
黄斑変性、網膜前膜、黄斑円孔、黄斑浮腫(糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症などに伴う)、網膜剥離、中心性網脈絡膜症
など多数あります。
それぞれ好発する年齢や症状、経過など異なりますが、自覚症状のみで病気を鑑別することは困難です。
OCTという黄斑部の断層像を見る検査があり、これにより診断が可能です。
治療は、それぞれの疾患により異なります。網膜剥離や、出血を伴う黄斑変性など、緊急を要する病気もあります。
『物がゆがんで見える』症状がありましたが、早めに眼科受診することをオススメします。