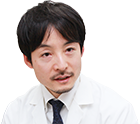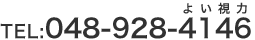9/18(土)は、台風のため臨時休診とさせて頂きます。
今回の台風は予測進路が安定しないため、結果問題なかったとなる可能性も高いです。しかし、万が一を考え、患者様及びスタッフの安全を最優先とさせて頂きます。
ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
目のかゆみは、主に『アレルギー性結膜炎』が原因となります。
アレルギー性結膜炎は、『季節性』と『通年性』に分けられます。
『季節性』は、スギ花粉のような季節性の花粉が主な原因となります。症状は毎年同じような時期に出て、時期が過ぎれば改善します。
『通年性』は、ホコリやハウスダストなど、身の回りにあるアレルギー物質が原因となります。また、動物を飼っていると、動物の毛やダニなどが原因となることもあります。
治療は、目薬が中心となります。目薬の種類は、原因問わず共通となります。
また、原因が分かっていれば、そのアレルギー物質に触れないことが重要です。そのために、メガネやゴーグルも有効です。
かゆくて目をこすってしまうと、角膜に傷や、ものもらいのような感染を引き起こします。
我慢できないかゆみがでるようでしたら、眼科への受診をオススメします。
『物がゆがんで見える』という症状は、主に網膜の中心である『黄斑』の障害で起こります。
黄斑の病気は、
黄斑変性、網膜前膜、黄斑円孔、黄斑浮腫(糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症などに伴う)、網膜剥離、中心性網脈絡膜症
など多数あります。
それぞれ好発する年齢や症状、経過など異なりますが、自覚症状のみで病気を鑑別することは困難です。
診断には、OCTという黄斑部の断層像を見る検査を行います。多くの病気は、OCTで判別可能です。
治療は、それぞれの疾患により異なります。網膜剥離や、出血を伴う黄斑変性など、緊急を要する病気もあります。
『物がゆがんで見える』症状がありましたが、早めに眼科受診することをオススメします。
『黒いものが飛んで見える』
『髪の毛のようなものが動いて見える』
『アメーバみたいなのが見える』
などの症状を『飛蚊症』と言います。
多くの場合、自然に出てくるもので悪いものではありません。
ただし、治療法はないので、そのまま様子を見ることになります。
1か月以内であれば、飛蚊症が減少することもありますが、それ以降も残るものは、そのまま残存する可能性が高いです。
一方、まれに『網膜剥離』や『硝子体出血』などの病気の症状として出てくることがあります。
特に『墨汁を流したような黒い(赤い)ものが見える』などの飛蚊症の量が多い場合、これらの病気が原因となっている可能性があります。
飛蚊症が自然に出たものか、病気が原因か、自覚症状で判別するのは困難です。そのため、眼科で検査をすることをお勧めします。
病気が原因の場合、病気に応じた治療を要します。特に網膜剥離の場合、緊急での対応が必要となるため、飛蚊症が出た際には、なるべく早めに受診したほうがよいです。
飛蚊症に対する検査として、目薬で瞳を開く『散瞳検査』を行います。この目薬をさすと、5時間程度見えにくくなり、車の運転や細かい字を見る作業などができなくなります。
そのため、眼科受診の際は、車やバイクではなく、徒歩や公共交通機関を利用してください。
また、目薬の効果が出るまでに時間がかかるため、当院では診療終了時刻の1時間前までの受診が必要となります。
時間には余裕をもって、お越しください。

本日の院長ランチ、テイクアウト編は
割烹料理『源氏』の
香味ダレ三元豚のお弁当です。
源氏は久しぶりでしたが、野菜などが上品で美味しいです。
他では味わえないお弁当ですので、是非。
白内障手術に際し、悪いほうの目だけでいいか、それとも両目とも手術したほうがいいか、というご相談をよく頂きます。
まず、両目手術のメリットですが、
・術後の左右のバランスがよい
・ピントの位置を自由に選ぶことができる
・眼鏡を早く作成できる
・検査などが一度で済む
・同じ月だと、限度額により、自己負担額が安くなる
などが挙げられます。
両目ともある程度白内障が進行している場合、いずれ両目とも手術することになるため、両目とも手術をしたほうが、メリットは大きいと考えます。
一方、片目のみ白内障が進行しているが、他目は比較的視力良好の場合は、視力や度数の左右差などを考慮したうえで、片目か両目かを相談して決定します。
判断はそれぞれの目の状態によって変わってきますので、迷ったら一度ご相談頂ければ幸いです。

今月もスタッフが置き看板にカワイイ絵を描いてくれました。
いつもありがとうございます。
ミスタードーナツ的な猫のキャラクターです。
この絵を見ていると、ドーナッツが食べたくなります。
受診の際は、帰りに眺めて帰って下さい。
手術当日は、午後1時40分までに受診していただきます。
手術の準備として、目薬とキャップの着用を行います。その後、順番で手術を行います。
手術の順番は、目の状態などから、事前にこちらで決めさせていただいております。
手術時間は、10分程度です。ただし、手術の準備と片付けがあるため、手術室での滞在時間は20分程度です。
手術後は、会計して終了となります。
安全な準備のため、手術の方は同時刻にご来院頂いております。最後の方で、3時半頃に手術終了予定です。しかし、場合により終了時刻が遅れることがあります。
予めご了承ください。
普通免許では、矯正視力0.7以上が必要となります。
そのため、矯正視力が0.7以上出た時点で車の運転が可能となります。
白内障手術は安全性が高く、合併症などが起こる可能性はとても低くなっています。しかし、ごくまれですが、様々な合併症が生じて、視力が低下する可能性もゼロではありません。
また、手術後の視力は、角膜、網膜、視神経などの、目の他の部分の機能に依存します。白内障以外の病気があれば、手術は無事終わっても、視力が改善しないこともあります。
というわけで、手術前に運転できる視力が出ると保障することすらできず、いつから運転できるとお約束することはできません。
一方、経過良好で術後視力が良好な場合ですが、手術翌日から視力がばっちりでることもあれば、1~2週間程度改善に時間がかかることがあります。
また近視の場合、眼鏡の度数が変わることが多いです。その場合、眼鏡を作成し直す必要があります。
結論ですが、手術後いつから運転できるかはわからないため、しばらくは運転する用事は控えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
白内障手術をした直後はよく見えていたけど、数年して視力がまた低下した、という方がいます。
まず、一番多いのが
『後発白内障』
です。
水晶体は、『嚢』という透明の袋で包まれています。白内障手術は、嚢を残して、中味の濁った水晶体を取り除き、残った嚢に眼内レンズを挿入します。
嚢は、最初は透明ですが、時間が経つと、白くにごってしまうことがあります。これが後発白内障です。
症状は、白内障と同様に視力低下が生じます。
こちらは、外来にてレーザー治療で治ります。レーザー治療は5分程度で可能です。
それ他、白内障とは関係のない病気の発症が原因となることがあります。
白内障手術を要する方は高齢者が多いため、加齢性黄斑変性、緑内障、網膜静脈閉塞症、黄斑前膜など、様々な目の病気を発症する恐れがあります。
そのため、白内障手術が無事終了し、経過良好でも、定期的な診察は続けておいた方がよいかと存じます。