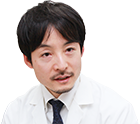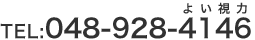手術当日は、午後1時40分までに受診していただきます。
手術の準備として、目薬とキャップの着用を行います。その後、順番で手術を行います。
手術の順番は、目の状態などから、事前にこちらで決めさせていただいております。
手術時間は、10分程度です。ただし、手術の準備と片付けがあるため、手術室での滞在時間は20分程度です。
手術後は、体調に問題がなければ会計して終了となります。
安全な準備のため、手術の方は同時刻にご来院頂いております。最後の方で、3時半頃に手術終了予定です。しかし、場合により終了時刻が遅れることがあります。
予めご了承ください。
現在、白内障手術を申し込むと、GW明けの5/6以降となります。
5月の手術枠は、まだ比較的空いていますが、GW中は休診となるため、GW明けは手術が混み合うことが予想されます。5月中に手術をご希望の方は、早めに受診していただくことをオススメします。
視野検査は、平日は同じく5/6以降となります。一方、土曜日は予約が6月まで埋まっております。そのため、視野検査を早めに希望の方は、平日でスケジュールを調整して頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
世界一のスタッフ満足度を目指して・・・。
今年のテーマ『小さな幸せのおすそ分け』
【松下幸之助の『道』朗読会】
当院の経営方針は、パナソニック創業者の松下幸之助氏と京セラ・KDDIなどの創業者の稲森和夫氏の教えを基盤としております。特に今日のような困難なご時世には、両氏の教えが身に沁みます。
そこで、コンビニお惣菜シリーズ終了後は、『道』朗読会を行います。事前にテーマを配布し、当日担当者に朗読してもらいます。
今刺さる内容もあれば、5年後10年後に気付かされるものもあると思います。
お楽しみに。
まず、診察にて手術適応のある方に、手術の希望につき伺います。
手術希望がある場合、手術や術前検査の日程を予約していきます。
当院では、月曜と木曜の午後が手術日となっております。
また、手術翌日は、9時半から診察を行います。そのため、手術日午後と翌日午前中に受診の必要があります。
さらに術前検査のため、手術までに2回の受診が必要となります。
これらの日程をすべて決定した時点で、手術が決定となります。
なお、電話での予約や代理人による予約はできませんので、ご了承ください。
S社とのミーティングを終えた私は、指摘された懸念事項などにつき話し合うために、A氏に電話しました。すると、いつもの穏やかな口調から一転、かなりきつい口調で
「開業するときは、反対勢力が出るものです!気にしてたら開業なんてできないですよ!!」
と一喝されました。
S社とは、開業活動に協力してもらうパートナーという位置づけだったため、反対勢力という言い方には、違和感を覚えました。
この時初めて、A氏への信頼が揺らぎ、この開業への不信感が生まれました。
一方、このままA氏の言うとおりにしないと、一生開業できない、という焦りもありました。
まさに引くも地獄、進むも地獄です。
そんな中、会計事務所の勧めで、物件の契約書のリーガルチェック(契約書を弁護士にチェックしてもらう)をし、問題なければ契約する、という方向で、A氏と話がまとまりました。
しかし、この後とんでもない大事件が起こりました。
続く
病態 ばい菌が入り、まぶたに炎症を起こす。
症状 まぶたが腫れる、痛み、めやに、充血、しこりができる
好発年齢 全年代
原因 何もないことも多い。こする、ゴミが入るなど。
進行 急激に発症。2週間程度で自然に改善することが多い。
片目or両目 片目
治療 目薬、軟膏。改善しない場合、手術することがある。
病態 脈絡膜から網膜下へ水がたまる
症状 視力低下、視野の中心が見えにくい、ゆがむ、物の大きさが左右で違って見える
好発年齢 40~50歳台の男性
原因 不明。ストレスなどが原因とも言われている。
進行 急に発症するが、半年~1年程度で自然に改善することが多い。
片目or両目 片目
治療 飲み薬。なかなか治らない場合や再発を繰り返す場合、特殊なレーザー治療の適応となることがまれにある。
病態 黄斑部に新生血管ができて、出血や浮腫などを引き起こす
症状 視力低下、視野の中心部が見えなくなる、ゆがむ、物が大きさが左右で違って見える
好発年齢 60歳以上
原因 主に加齢、紫外線、食生活
進行 数年単位で徐々に進行することが多いが、急激に悪化することもある
片目or両目 まずは片目。長期的には両目になることが多い
治療 硝子体注射。場合により手術適応となることもあり。
世界一のスタッフ満足度を目指して・・・。
今年のテーマ『小さな幸せのおすそ分け』
『第5回コンビニ弁当&お惣菜』
オススメのコンビニ弁当&お惣菜は、
セブンイレブンの『たことブロッコリーバジルサラダ』です。
たことブロッコリーに加えて、ジャガイモ、枝豆、(セロリ)が入っています。想像通りの味ですが、タコが入っているのは珍しく、バジルは臭みがなく、ちょうど良い塩味です。税込み267円です。安くはないですが、少し物足りないとき、もう一品ほしいときにオススメです。